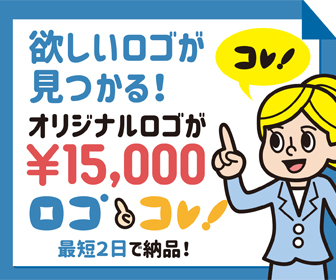目 次
電動アシスト自転車乗りにとってよくある残念な会話
「昨日は80kmサイクリングしてきたよ」などと、自転車が趣味じゃない人にプチ自慢すると、相手からは「え~!すごいね」というリアクションが返ってきて、嬉しくなります(私は単純な人間です)。

しかし、「電動アシスト自転車で行ったのだけどね」と一言付け加えると、あからさまに「な~んだ」という顔をされてしまいます。
それで、「電動アシスト自転車はオートバイやカブと違うんだよ。
例えば、時速18km近くだと、漕ぐ力の3分の1だけしかアシストしてくれない。
残りの3分の2は自力で漕がないといけないので、楽なわけではないんだよ。」
とこちらは説明しはじめます
ところが、一生懸命に説明しても、相手は関心を示さず、聞いているのかいないのか・・・
これは、電動アシスト自転車でスポーツをしている人にとっては、あるある的な会話だと思います。
多くの人が、「電動アシスト自転車って、楽だから運動にならないんでしょ」という思い込みを持っているように思います。
この思い込みに関する面白い資料をたまたま見つけたので、シェアしたいと思います。
http://www.hokuriku-pe.jp/?tid=100081

この資料が素晴らしいのは、感覚ではなく、実際に実験したデータに基づいているところです。
これは、金沢大学の先生などを構成員とする北陸スポーツ・体育学会と金沢市との共同事業として行われている「金沢サイクルFITプロジェクト(KCFP)」が公開している「自転車活用、健康への活かし方」という資料です。
この資料を読むと、電動アシスト自転車が運動になるか、ならないかは、簡単に言うと「乗り方による」ということがよく分かります。
あまり運動にならない電動アシスト自転車とは
これは端的に言うと、「ママチャリ風電動アシスト自転車」の場合です。

ママチャリは、重い買い物荷物や子供を乗せているときにぐらついても、すぐに足をつけられるように、サドルがかなり低くセットされています。
サドルが低いと、自然にペダルの回転数が低くなり、スピードは上がりません。
さらに、前傾姿勢ではなく、サドルに対して直角に座っているので、上半身の力を使いづらいことも、スピードが上がらない原因になります。
このようなことからママチャリの運動効果は低いということになります。
下の図は、「自転車活用、健康への活かし方」資料からの抜粋です。
20~50歳の女性20名が26インチ軽快車(ハンドルの位置が高く、サドルの高さが低いママチャリ風自転車)の電動アシスト自転車で、平坦な道と坂道を走った時の運動の強さを測定した結果です。
縦軸のHRRは「最大心拍予備量」のことで、勾配3%の緩い坂での心拍数強度は35±11%(アシスト・オン)と39±11%(アシスト・オフ)でした。
健康に良い心拍数強度は50~60%がお勧めとされているので、アシスト・オンの場合、殆どの人の運動強度が足りないということが分かります。

また、次の図は、勾配6%の坂をママチャリで上った場合です。
この図を見ると、勾配が6%に増しても、アシスト・オンの場合、大半の人の心拍数強度が50%以下で、やはり運動強度が足りていないということです。

このように、「ママチャリ風電動アシスト自転車」は、平坦な道はもちろん、たとえ坂道であっても、あまり運動にならないことが、データで分かります。
「電動アシスト自転車って、楽だから運動にならないんでしょ」という意見は、「ママチャリ風電動アシスト自転車」については間違いではないと言えそうです。
運動効果のある電動アシスト自転車とは
これは、結論から言うと、「クロスバイク風電動アシスト自転車」(勿論、e-bikeも)だと運動効果を得やすいということです。
「クロスバイク風電動アシスト自転車」はサドルを高めにセットし、前傾姿勢をとりやすくなるので、ペダルをより高回転で回せるので、スピードを上げやすくなります。
また、ギアが多くついていることが一般的で、適切なギヤ選択をすることで、スピードに乗りやすくなります。
スピードが速くなるにつれて、アシスト比率が低下しますので、アシスト・オンの場合でも、自力でペダルを漕ぐ割合が高くなり、健康寿命を延ばすのに効果のある運動強度を得ることができます。

実際にデータをみてみましょう。
下の図は、総勢14名の人(平均年齢32歳)が「クロスバイク風電動アシスト自転車」で走った結果の平均値です。
健康づくりに役立つ「中程度(ややきつい)」の運動強度で走れていることが分かります。

次の表は、高齢の自転車愛好家19人のアシスト・オンでの走行実測結果です。
私も高齢者と言われる歳になりましたので、非常に興味があります。
さて、その結果は、運動強度の平均が71.1%と、健康に効果のある運動強度となっています。
50~60%でも効果があると言われているので、この数字はばっちりです。
若い自転車乗りの人からみると、「え~!こんな低速でいいの?」と思うかもしれません。
しかし、このくらいのスピードで気持ちよく走るので十分です。

上記の実験に参加した72歳の女性の方の詳細データが下図です。
72歳でも心拍数を160くらいまで上げられているのは素晴らしいですね。
このように高齢の人でも長時間、健康に効果のある運動強度を持続できています。

私は健康のために電動アシスト自転車に乗っていて、運動になっているという実感はありました。
しかし、「自転車活用、健康への活かし方」のデータに基づいた資料のおかげで、より客観的に確信することができました。
まとめ
「電動アシスト自転車が運動になるか、ならないか」は、上記のように「乗り方による」ということになります。
- サドルを高めにセットするとともに、サドルの前後位置を調整して前傾姿勢をとれば、ペダルを早く回しやすくなります。
- ペダルを早く回せば、速度が上がり、アシストの割合は低くなっていきます。
そして、時速24kmを超えると、アシストはゼロになるようにどのメーカーの電動アシスト自転車も作られています。 - そのため、最大酸素摂取量と心拍数は高くなり、下半身を中心に筋活動量も高くなり、健康づくりに役立つ運動をすることができます。
ママチャリ風電動アシスト自転車は、高めのハンドル、低めのサドルを想定してフレームが設計されているので、上記のようなセッティングにするのは難しいと思います。
したがって、電動アシスト自転車を運動の道具として使うには、クロスバイク風電動アシスト自転車を選ぶ必要があります(勿論、e-bikeもOKです)。
それから自転車に乗っている時間も大切です。
いくら上記のように乗車姿勢をセッティングしても、短時間(すなわち、短距離)では効果が薄いです。
下の記事に、自転車に乗っている人の8割以上が、たった5km以下の移動にしか利用していないというデータを紹介しました。
運動効果を得るためには、少なくとも20分以上はサイクリングをする必要があります。
私はブリヂストンのクロスバイクである、TB1e(下の写真)に乗っています。
サドルは高めにセットして、前傾姿勢をとれるようにしています。
前後に大きなカゴを取り付け、20kmや30km先のショッピングセンターやホームセンターによく買い物に行きます。
TB1eはその高機能の割に値段がリーズナブルなので人気がありますが、私も非常に気に入っています。